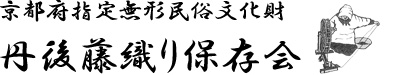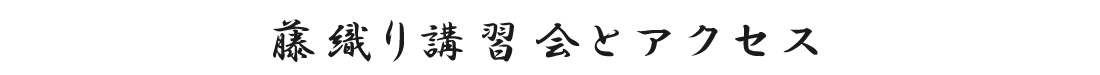上世屋へのアクセス・藤織り講習会
上世屋に残る藤布は日本古来の織物です。藤布は上世屋で山着や漉し布などに使われていました。
2025年現在、講習会は開講しておりません。
藤織り伝承交流館の開館日は、8月を除く5月から11月の第1、第3土曜日です。
(2025年は、5/3、5/17、6/7、6/21、7/5、7/19、9/6、9/20、10/4、10/18、11/1、11/15)
開館時間は10時から16時です。
見学は事前にメールにてご予約ください。なお、人数の上限をもうけさせていただいております。ご理解をいただけますと幸いです。
第37回「藤織り講習会」受講者募集要項(※募集は終了しています)
■ 趣 旨 ■
わたしたちの丹後藤織り保存会は、京都府指定無形民俗文化財「丹後の藤織り」の保護団体として、丹後の山村・宮津市上世屋に残る藤織りの技術の継承と普及を目的として活動をつづけている会です。
この藤織りの伝承技術を後世に伝えていくため、上世屋地区を中心に講習会を開催して、今年で39年目を迎える息の長い取り組みを行なっています。
藤織りの工程は、ゴツゴツした藤蔓の木の皮の繊維からおよそ10工程をとおして柔軟な布へと変身させます。藤織りの楽しさや難しさを、受講者自ら山へ入って藤を伐るところから機で織り上げるまでを体感していただくことによって、後継者の育成をはかっていきたいと考えています。
ぜひ、この機会に木綿が普及する以前の樹皮繊維である「藤織りの世界」を体験してみませんか。織物経験の有無は問いません。まったく織物の経験のない方、山歩きが好きな方、なんでも自分で作りたい方、どなたでもご参加をお待ちしています。
主 催
■ 丹後藤織り保存会
開催時期
■ 2024年5月~11月〔6回の講座〕
会 場
■宮津市上世屋 藤織り伝承交流館(旧・世屋上分校)
講習会日程および講習内容
第1講座 5月18日(土) 開講式・藤伐り・藤剥ぎ
第2講座 6月15日(土)・16日(日) 灰汁炊き・藤扱き
第3講座 7月20日(土) 藤績み・撚り掛け・枠取り
第4講座 9月21日(土) 整経・機に負わせる
第5講座 10月19日(土) 機織り
第6講座 11月16日(土) 機織り・修了式
※各会、9時集合、9時半スタート、15時半ごろ終了になります。
※第2講座のみ、土曜日と日曜日の開講になります。土曜日の夜には、懇親会を行います。
宿泊・懇親会はペンション自給自足となります。
講 師
■ 丹後藤織り保存会員
募集定員
■募集定員 5名 〔募集期間は4月24日(水)まで 〕
※すべての講座に参加できる方。
※講習会の修了後は、丹後藤織り保存会の会員として活動してくださる意思のある方。
※定員を超えて応募があった場合は、抽選とさせていただきます。
参加費・注意事項
■ 受講料について
受講料(全6講座分)18.000円
■注1.現地までの往復の交通費は各自でご負担ください(現地集合・現地解散)。
■注2.テキスト代・第1講座の傷害保険料は受講料に含まれます。
■注3.第2講座の宿泊費は、受講料に含まれていません。
■注4.第1講座で徴収します受講料は、講習会途中でやめられても返金はいたしません。
■注5.工程のなかの糸づくり(藤績み)では、家へ持ち帰っての宿題があります。
申し込み方法
以下のオンラインサイトにて必要事項を記入のうえ送信してください。
申し込み 問い合せ先
〒626-0227 宮津市字上世屋850 藤織り伝承交流館内
E-Mail;tangofujiori@gmail.com
アクセス
所在地
〒626-0227宮津市字上世屋
車でお越しの場合

■京都市内方面から
京都市内から
京都縦貫道で沓掛から与謝天橋立ICを出て国道176号を通る。
国道178号へ入り伊根方面へ。
日置の交差点を左折し、75号を世屋高原へ。
そのまま道なりに進む。
※最寄駅(宮津駅、橋立駅)から公共交通機関がございませんので、お車でお越しください。
公共交通でお越しの場合
■電車《京都丹後鉄道》
JR京都駅から京都丹後鉄道 天橋立駅まで、特急を利用して約2時間。
宮津駅からタクシーのご利用。〈約50分〉
★日交タクシー 天橋立営業所 0772-22-4121
■高速バス
京都駅発の高速バスに乗り、天橋立駅で下車。
天橋立駅からは、タクシーのご利用。〈約50分〉
★日交タクシー 天橋立営業所 0772-22-4121